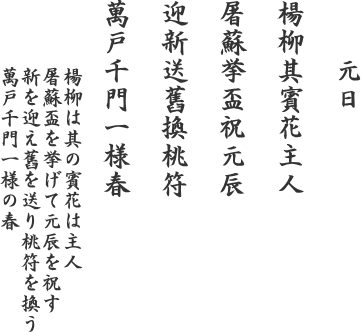
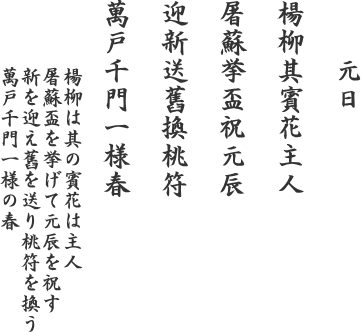
柳は元日の客人、花は主といった風情で彩を添えている
屠蘇の盃を挙げてこの元日のよき日を祝う
新年を迎え、旧年を送り、魔よけの桃符も新たにいずれの家々も一様にめでたい春を迎えたことだ
この詩は亀岡文殊堂奉納詩歌百首の冒頭を飾る詩であり、元日のおめでたい情景を詠んだものである。。
柳と花は、春の風物として、兼続が20歳の時に作ったという「歳旦」の詩にも登場する。(「歳旦」では「花」は梅の花であるが、この詩では単に「花」とあるだけである。おそらく梅の花であろう。)
柳の緑と花(梅)の淡い紅色が、元旦の風景に華やかさを添えている。屠蘇で新年を祝い、桃符も新しいものに取り替えた。(「桃符」とは、桃の木で作った魔除けの札のことで、元旦などに門戸にとりつける、昔の中国の風習である。)いずれの家も一様に春正月を迎えた、という、一見なんということもない元日の穏やかな情景が描かれた詩である。
だが、この年(慶長7年)、果たして兼続たち上杉家の諸士たちは、「なんということもなく」正月を迎えられたのであろうか。
上杉家の米沢転封が決まり、米沢に移って間もなく年が改まった。落ち着いて新年を祝うという雰囲気ではなかったであろう。「萬戸千門一様春」というにはあまりにもかけ離れた現実が兼続たちの目の前にはあったはずだ。
だが一方で、どうにかして今年も新年を迎えられたという安堵の思いもこの結句からは感じられる。
奉納詩歌百首の冒頭で、兼続が新年を寿ぐ詩を詠んだことは、だからこそ大きな意味を持つ。単なる部立ての順番なのではない。
どの家も穏やかな新年を迎えることができますように―それは、そのとき、その場に集った人々の誰もが心に抱いた願いであっただろう。その願いを兼続は代弁して、高らかに吟じあげたのである。
(2006.元旦記ス)
| SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||
